
東京商工リサーチの記事によれば、2024年時点で自己資本比率が50%以上の企業は全体の44.0%に達し、財務の安全性を高めていると。
一方で、債務超過の企業も13.7%に上り、特に建設業では約2割の企業が債務超過に陥っているとの事でした。
という事で、自社の直近の決算では自己資本比率が50%を超えていない為、この結果を元に今後取るべき対応等のアドバイスをChatGPT4oに壁う打ちしてみた。
回答としては、2024年の建設業倒産件数は1,313件と、前年比で約20%増加。
これはコロナ禍直後の反動だけでは説明がつかない、構造的な問題が浮き彫りになってきた証拠である。
特に注目すべきは、「人手不足倒産」と「資材高騰による採算悪化」が二大要因になっている点。
加えて、働き方改革関連法の影響による「2024年問題」や、脱炭素社会に向けた設備投資負担など、多重苦が中小建設業者を直撃している。
これらの影響を受けやすいのが、まさに中小・零細規模の建設業者です。
特定の元請けや特定業務に依存している場合、発注減や価格交渉の不利が直撃します。
また、限られた人材で現場を回している企業ほど、人的余力がなく、業務遅延や品質低下を引き起こしかねません。
こうした状況に立ち向かうためには、次のような対策が急務です。
①収益構造の見直しと“原価の見える化”
粗利率を意識した見積もり作成を徹底すること。まだ「材料費+人件費+α」といったざっくりした感覚で価格設定している事業者は要注意です。原価管理をデジタル化し、案件ごとの利益率を把握する体制を整えましょう。
②元請け依存からの脱却──自社受注力の強化
ホームページの整備、SNSやGoogleマップの活用、地域イベントでの露出など、元請け頼みの受注構造から脱却するには、「自社を知ってもらう」努力が必要です。少額でも直接受注できる案件の積み上げが、安定経営の鍵になります。
③人材の“定着”と“多能工化”への投資
単に人を増やすのではなく、今いる人材のスキルアップと離職防止が重要です。資格取得支援や福利厚生の強化、ワークライフバランスを意識した職場改善が、結果的に採用コストの削減にもつながります。
④外注・協力会社との「共存型パートナーシップ」構築
外注先に価格を叩くような関係は、長期的には自社の施工力を失います。パートナー企業と施工計画やコスト情報を共有し、利益を分け合える関係性を築くことが、繁忙期や緊急対応でも力を発揮します。
建設業界は今、大きな転換期にあります。過去のやり方では立ち行かない時代がすぐそこまで来ています。いまこそ、自社の足元を見直し、「生き残るための経営」を再設計するタイミングです。
対策内容は兎も角、AIの翻訳は分かりやすいなとつくづく。
それでは、また。
No.6711
★モデルハウスへのご来場予約はこちらです★


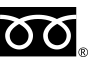 0120-704-991
0120-704-991  メールで資料請求
メールで資料請求





