
某業界紙の記事が非常に興味深く読めたので、要約すると、国土交通省が2024年度に行った調査結果をもとに、2025年3月から公共工事に携わる職人さんたちの賃金(労務単価)が引き上げられることを伝えています。
特に、大工さんの賃金は6.3%、左官(壁や床を塗る職人)さんは6.8%上昇するとのことです。
これは、建設業界での残業時間の上限が厳しくなり、その対応として賃金が見直された結果です。
また、地域ごとの大工さんの賃金も紹介されており、例えば東京都では1日あたり3万400円、宮城県では3万3900円とされています。
さらに、労務単価には事業主が負担する経費は含まれておらず、例えば労務単価が2万4852円の場合、事業主が実際に負担する総額は約3万5041円になると説明されています。
上記を勘案し、今後の建築業界における単価上昇がエンドユーザーに与えるネガティブ要素として考えてみた。
① 建築コストの上昇 → 住宅価格の高騰
大工や左官をはじめとする職人の賃金が上昇することで、住宅建築費全体のコストが増加する。
これは注文住宅、建売住宅、リフォームなどあらゆる分野に影響し、結果的にエンドユーザー(施主)が負担する金額が増える可能性がある。
特に、すでに住宅ローン金利の上昇が進んでいる中で、建築費の上昇が重なると、家を建てる人にとってはさらに負担が大きくなる可能性がある。
② リフォーム・修繕費の増加
新築だけでなく、リフォームや修繕工事の費用も上がることが予想される。
特に、以下のような工事では職人の技術が求められるため、単価上昇の影響が大きい。
- 外壁や屋根の補修
- 水回りのリフォーム(キッチン・浴室・トイレ)
- 床や壁の張替え(フローリングやクロス)
- 基礎・耐震補強工事
「ちょっとした修繕工事のつもりが、想定以上の金額になった」といったケースも増えたという、事例や記事が各メディアで増えるかも。
③ 工期の長期化(人手不足の加速)
現在、建設業界は慢性的な人手不足に陥っていると言える。
賃金が上がることで新しい職人が増えればよいのですが、それだけで解決できる問題でもない。
建築コストが上がりすぎると、新規の住宅着工件数が減少し、逆に職人の仕事が減る可能性があります。
そうなると、
- 新築やリフォームを頼んでも、職人が見つからず工期が長くなる
- 予約が取りづらくなる という問題が発生するかもしれません。
④ 中小工務店・職人の経営悪化
大手ハウスメーカーは価格調整や企業努力で対応できるかもしれませんが、中小の工務店や個人の職人は、単価上昇に対応しきれず経営が厳しくなる可能性があります。
- 値上げすれば顧客が減る
- 値上げしなければ利益が圧迫される
このようなジレンマに陥ると、結果的に小規模な工務店の廃業が増え、エンドユーザーが「信頼できる地域の工務店に頼みにくくなる」ことも考えられる。
⑤ 住宅市場の二極化
建築費の上昇が続くと、
- 高所得層向けの高価格住宅
- 低コストの規格住宅・ローコスト住宅
の2極化が進む可能性がある。
高価格帯の注文住宅を建てられる層は問題ありませんが、中間層が「予算オーバーで希望の家が建てられない」ケースが増えると、市場全体が不安定になる恐れもある。
結論:エンドユーザーへの影響まとめ
✅ 住宅価格・リフォーム費用の上昇 ✅ 工期の長期化や職人不足の深刻化 ✅ 中小工務店の経営悪化による選択肢の減少 ✅ 住宅市場の二極化が進み、中間層が苦しくなる
これらの要素を考えると、今後エンドユーザーは「いかにコストを抑えつつ、質の高い住宅を建てるか」をより慎重に考える必要があるので、これらの問題点の解決にあたる具体的なソリューションを実行できれば、決して悲観する市場ではなくなるはずで、自社が取り組むべきテーマとして、遣り甲斐もある。
会社一丸で頑張りましょう(^^♪
それでは、また。
No.6678
★モデルハウスへのご来場予約はこちらです★


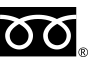 0120-704-991
0120-704-991  メールで資料請求
メールで資料請求





