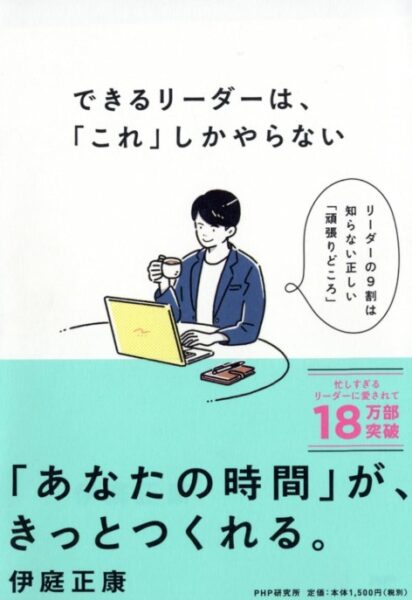
2024年12月の課題本。
「できるリーダーは、「これ」しかやらない メンバーが自ら動き出す「任せ方」のコツ」伊庭 正康 (著)
リーダーシップにおいて重要なスキルの一つは「任せる力」。
この書籍は、部下を初めて持つ管理職や、組織の責任者として業績を伸ばせず悩んでいる方、さらには次世代リーダーの育成を視野に入れた方にとって、実践的な指南書かと。
本書を通じて理解できる点は、「任せる」という行為が単なる仕事の分配ではなく、組織全体の成長を促す重要な要素であるという点。
著者は、リーダーの役割を「全体を見渡し、メンバーの力を引き出すこと」と定義している。
この中で、特に強調されているのが「信頼」。
リーダーがメンバーに信頼を寄せることで、メンバーは自ら責任を自覚し、主体的に動き出すようになると。
本書では、この信頼を築くための具体的な方法が丁寧に解説されている。
例えば、「任せる範囲を明確にすること」が成功の鍵であると著者は指摘している。
曖昧な指示ではなく、具体的なゴールや期待を共有することで、メンバーは自身の役割を正確に把握し、成果を出しやすくなると。
また、任せた後も「干渉しすぎないこと」が重要で、リーダーが過度に介入せず、メンバー自身で問題を解決させることで、彼らの成長を促すことができると述べている。
このようなアプローチは、管理職として成長を目指す方にとって極めて実用的。
さらに印象深いのは、「失敗を許容する文化をつくる」という章。
失敗は任せる過程で避けられないものですが、失敗を恐れる環境では、メンバーのチャレンジ精神が当たり前に失われる。
著者は、失敗を学びの機会と捉え、それを共有してチーム全体の成長に活かすことの重要性を説いている。
この姿勢は、組織を運営しながら人材を育成するうえで欠かせない視点かと。
また、リーダーとしての自己管理の重要性についても触れられている。
「すべてを自分で抱え込まない」ことは、特に組織運営において重要です。リーダーが過剰に負担を抱えると、冷静な判断ができなくなり、チーム全体のパフォーマンスに悪影響を与える可能性が当たり前にある。
適切な任せ方を実践することで、リーダー自身が余裕を持ち、戦略的な判断を下せる環境を作ることが重要。
本書を参考に、任せることの奥深さを探求し、実践を重ねることで、信頼関係を基盤とした成果を生むチーム構築が出来れば理想的かなと思う。
それでは、また。
No.6634
★モデルハウスへのご来場予約はこちらです★


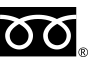 0120-704-991
0120-704-991 メールで資料請求
メールで資料請求






