
某建設業界紙の記事で、「フラット35申請状況、前期比150%の大幅増」「9月首都圏新築戸建て、2カ月連続上昇 全体で上昇基調が続く」という記事が。
そこから読み解く、これからマイホームをいう方々にとっての判断軸を簡単に以下で。
記事の内容を要約すると、
1.新築戸建の価格は首都圏で上昇基調が継続。 2025年9月の平均価格は4,831万円(前月比+0.1%)、東京都・横浜/川崎・さいたま・千葉西部などで2017年以降の最高額を更新。前年比も+5.6%で13カ月連続上昇です。
2.固定金利の「フラット35」利用が急増。 2025年7〜9月の申請戸数は前同期比150.7%と大幅増。10月時点の金利は年1.89%前後(融資率9割以下)で、金利上昇リスクを避けたい層に支持が広がっています。
まとめると、価格は強含み×固定金利の安心感が評価されている局面。 「いつ買うか」は、家計の耐性(返済負荷)と金利観で決めるのが合理的かと。
東京都や横浜・川崎などで高値更新が続き、前年同月比でも上昇傾向です。
一方で住宅ローンは固定型の安心感に再注目。フラット35の申請は前年同期比150%超へ伸び、10月金利はおおむね1.8~1.9%台。先行き金利不透明感の中で「返済計画の見通し」を優先する層が増えています。
買うか待つかは“値ごろ感”ではなく“家計の耐性”で判断を。
目安は、
①返済負担率20~25%(共働きでも30%超は要注意)
②手取りの2~3割の余裕を確保
③可変を選ぶなら+1.0%の金利上昇に耐えられるか。
上昇局面で負けない進め方は、総予算(土地+建物+諸費用)の上限を先に固定し、仕様は優先順位で調整。
金利は固定を軸に、家計に余白が大きい場合のみ可変を“初期負担の軽さ”として限定活用。
立地は将来の売却・賃貸まで想定し、駅距離・生活利便・学区・災害リスクで加点。
加えて断熱・設備の性能を電気料金シナリオで30年の累計差まで見える化すると、実質負担を抑えられます。
「買ってよい人」は、返済負担率25%以内・生活の不確実性が小さい・性能重視で光熱費まで最適化できる方。
「待ったほうがよい人」は、転勤等の不確実性が高い、金利+1.0%で家計が崩れる、自己資金を確保できない方。
結論、相場は強含みでも“家計の耐性”が決め手になるのは、市況に関わらず常ですね。
それでは、また。
No.6928
★LINE登録はこちらです★
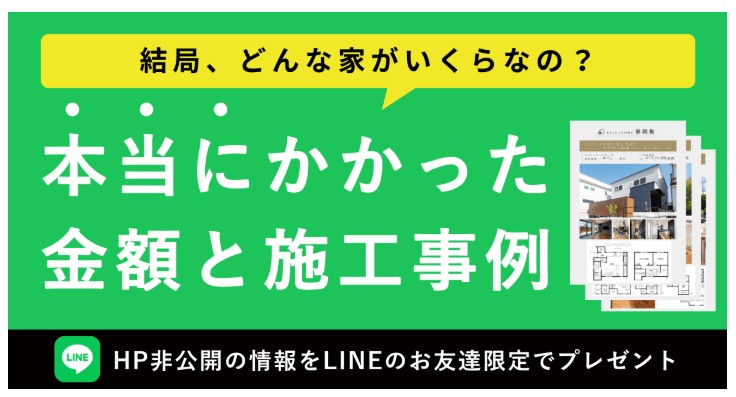

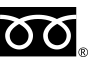 0120-704-991
0120-704-991  メールで資料請求
メールで資料請求





